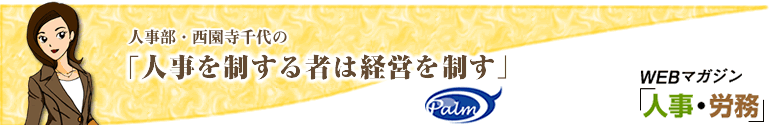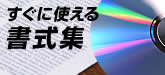←応援してね!
←応援してね!
前回に引続き、就業規則作成セミナーについてです。
作成した就業規則を従業員に公開しない会社の話を良く聞きます。
しかし、これでは全く作成した意味がありません。
従業員に全く周知されなかった就業規則には効力がないという判決もあります。
そもそも、従業員が就業規則の内容をよく理解して初めて、会社としての
規律を共有することが可能となるのです。
「周知すると従業員が自分の権利を主張してきて大変だ」との考えから、
就業規則を隠そうとする経営者も時折いるようですが、今の時代それは全くの
逆効果とのこと。インターネットを利用すると、誰でも働く人間の権利に関する
情報を知ることができます。「就業規則の明示は会社の義務」ということを知る
従業員は、会社に不信感を抱くでしょう。
さらに、インターネットで流布される情報の中身は必ずしも正しいもの
ばかりではなく、誤った知識をもとに会社への不信感を募らせるケースまで
あるとのことです。
そう考えると、就業規則は堂々と公開し、会社の方針を従業員に浸透させる
ためのツールとして、積極的に利用することが大切なのだということが、
良く理解できます。
就業規則の変更・作成

 ←応援してね!
←応援してね!
前回に引続き、就業規則作成セミナーについてです。
会社の資源である「人」「物」「金」「情報」のうち、人だけが唯一感情を
持っています。社内に暗黙のルールがはびこると、そのことへの不満や不安が
蔓延し、本来の業務に関係のないところに気持ちも時間もとられ、生産性は
大きく下がってしまいます。
また、理由を明確に理解した上で行動するのとそうでないのとでは、誰でも
やる気に大きな差が出ます。会社のルールを明確化し安心を与えること、そして
必要に応じて、社員のモチベーション向上につながるような、会社独自の規定を
盛り込んでいくことがとても重要になるのです。
確かに、会社は常に利益を上げて成長し続けなければならないものです。
上記のような理由を考えると、就業規則は、会社の成長のためのひとつの
ツールであり、業績と密接につながることが良くわかりました。
(つづく)
就業規則の作成なら

 ←応援してね!
←応援してね!
前回に引続き、就業規則作成セミナーについて。
就業規則には3つの段階があるとのこと。第1段階は、「法律上の
作成義務を守るための就業規則」第2段階が「会社のリスクを回避し、
裁判に勝つための就業規則」第3段階が「従業員のモチベーションを高め、
会社の業績を上げるための就業規則」という順です。
第1段階から第2段階へとすすみ、第3段階へ至って初めて完成します。
第2段階までは想像はつきますが、「従業員のモチベーションや会社の業績が、
就業規則と関係あるのかしら?」と、少し不思議に思いました。
就業規則は、服務規律など、従業員が守るべきルールを固くまとめたものだと
考えていましたから。
(つづく)
賃金制度の設計ならこちらへ

 ←応援してね!
←応援してね!
前回に引続き、雛形就業規則について。
就業規則を初めて作成する際、何らかの雛形を使用する会社がほとんどです。
けれど、行政機関などで無料入手できる就業規則をそのまま利用することは、実は会社にとってたくさんのリスクがあるようです。
何故なら、それらの雛形には、法律上の義務である規定とそうでない規定が盛り込まれていて、何の根拠もなく従業員に有利となる規定が多く含まれているからです。
確かに、法律の知識がないと、変更や削除が可能な部分がどこかなんて、わかりません。休職規定が法律上の義務ではないこと、それ故に就業規則の定め方次第であることなんて、今回のセミナーに参加して初めて知りました。
やはり、法律的に大きな意味がある就業規則は、専門家の力を借りて作成することが必要なのだな、とつくづく感じました。
(つづく)
就業規則の作成はこちら

 ←応援してね!
←応援してね!
現在、就業規則の見直しに着手しています。
以前耳にした「不利益変更」の怖さもあり、見直し自体は顧問の社会保険労務士の先生にお願いしています。
同時に、人事部として就業規則についてきちんと勉強して理解する必要性を感じ、(有)人事・労務さん主催の、就業規則セミナーに参加してきました。
セミナーでは、就業規則の持つ法律的意味合いから、リスクを回避させ、業績を向上させる就業規則の作りかたまで、わかりやすく解説をされており、大変勉強になりました。
わが社では、私が人事部に配属される以前から就業規則が作成されていたため新規作成に携わった経験はないのですが、大体の会社では、初めて就業規則を作成する際には、様々な方法で入手できる雛形を使うのが一般的なようです。
(つづく)

|