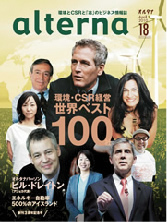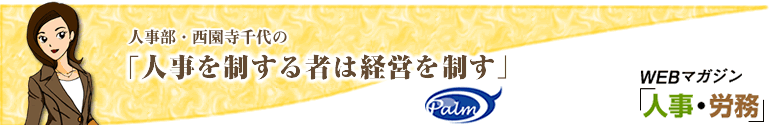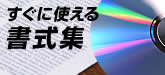先日、有限会社人事・労務さん主催の
日本ES開発協会の定例会に参加しました。
環境とCSRと志のビジネス雑誌 「オルタナ」編集長 森摂さんを講師にお迎えし、
「人と環境と社会にやさしいビジネス」をテーマにお話しいただく講演会でした。
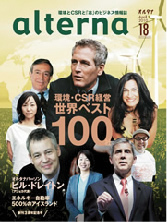
基調講演では、「ソーシャルビジネスという企業の新しい選択肢を探る」
と題して、「サッカー大国は実は環境大国であった」など、
森さんならではのユニークな視点から、日本の環境・資源への意識の低さや、
日本の将来が今ここにいる私たちの背にかかっていることを熱く語ってくださいました。
第二部は人事・労務の矢萩社長との対談でした。

テーマは「志の大きい企業が社会を変える」。
金融資本主義から知識資本主義、
そして今、絆を中心とした共感資本主義へと変化したこれからの時代、
経営者が社会貢献を意識したビジネスに転換し、
若者が知名度で企業を選ぶことを辞め、ソーシャルな企業を選ぶことが、
持続可能社会につながることを確認することができました。
持続可能経営の事例として、
オーガニックのスポーツウェアメーカーの、パタゴニアという企業があります。
パタゴニアでは、本来30%以上上げられる売り上げ成長率を、
年間2%までに抑え、100年後を見越して経営の意思決定をする
という方針を示しているそうです。

また、「ただ給料を上げるだけ、甘やかすだけがやさしさではない。」
というまさにESの考えにのっとって、
例えば社員はいつでもサーフィンに行って良い事になっていますが、
個人の責任は重く、チームとしての助け合いの精神も浸透させているそうです。
今回の定例会では、個々人のESに対する理解と、
ESとCSRの関わりに対する意識を高めることができました。
今後は私たちの会社でも、ソーシャルビジネスの意識を広め、
「本業を通じた社会貢献」を実現する志の高い企業・人材を創り出すために、
さらなる地域活動・啓蒙活動に励んでいこうと思います。

ある晴れた春の日、本当に久しぶりに地元をゆっくり、
のんびりと散策する機会に恵まれました。
わたしの地元はなかなかの田舎で、
少し歩くと山があったりこのご時世もはやめずらしいのかもしれない、
タニシの住む川が当たり前のように流れています。
仕事やめまぐるしく移り変わる日々のサイクルにほんの少しだけ疲れていた私は、
そんな愛すべき田舎に大いに癒された訳なのですが、
同時に少しだけ寂しく感じる場面に遭遇したのです。
確かに久しぶりに歩く我が町は相変わらず優しく、
多くの自然に囲まれていました。
しかし、その半面変わってしまった場所や風景もまた想像以上に大きいものでした。

子供のころに遊んだ原っぱは真新しい住宅街に、
ザリガニ捕りをした小川は大きな道路になっていたのです。
私は地元を離れて住んでいるわけではないのですが、
それでも改めてゆっくりと見渡してみると
「ずいぶん変わってしまったのだな」と実感させられるものですね。
子供のころは都心のように多くの娯楽施設もなく、
電車に乗らなければお洒落な服ひとつ手に入らない我が地元を
「まったく冴えないな」なんてよく思ったものですが、
不思議なことに今少しずつ発展してきている町を目にして
寂しさを感じている自分というのもどこか面白く少しだけ皮肉なものだと感じます。
それはきっと私にとっての地元というものの位置づけがいつのまにか
「暮らしていく場所」から、日々に少しだけ疲れてしまったり、
ほんのちょっとだけ日常から逃げ出したくなった時の
「とまり木」のような存在になっていたのではないかと思います。
以前の私の地元(上空からの写真)

きっと多くの皆さんにもこのような「変わらない場所」というものが
あるのではないでしょうか。
そしてそうした場所というものが、それが進化であれ発展であれ
変わってしまうことはそれぞれの人々にとって多かれ少なかれ
「痛み」を伴うのではないかと私は思います
時代の流れと多くの進歩や発展。
その裏には常に「変わらないもの」「変わってほしくないもの」が
少なからず犠牲になっているのだなと久しぶりの地元散策で考え直させられたのでした。
どんどんハイテク化していく現代社会。
だからこそその裏に隠れてしまいがちなかけがえのないものの存在に、
普段の生活のなかにおいても敏感でありたいものですね。
様々なエコ活動もここに一つの原点があるのかもしれません。
個人レベルの意識ひとつで、
あるいはとても大切な「場所」が守れるのかもしれないですね。
よし、とりあえず買い物袋でも手作りしようかしら。

有限会社人事・労務さんの横浜支社で、
6月9日(水)、横浜ソーシャルリンク主催、
~社会的なつながりを重視し、協働できる場を~において、
「人と社会と環境にやさしい社内制度の作り方」
と題したセミナーを実施していたので、参加させていただきました!
第1部では、ディヴィッド・ブラウアーが語った
「死んだ地球ではどんなビジネスも成り立たない」
という言葉が紹介されました。
社会における第5の競争軸として環境革新、持続可能性の追求という
新たな経営の視点について解説されました。

環境市場における、米国では既に30%以上を占めると言われるロハス層や、
まだ日本全体の1%ながらも、将来増加が予想されるグリーンコンシューマーの
存在等を説明していただきました。
また、米国の就職人気ランキングにおいて、NPO法人がディズニー等を
退けて上位にランクインした出来事など、現在の社会における変動の実態が分かりました。
第2部では、社労士としての経験に基づいた
「人と社会と環境にやさしい就業規則」
「人と社会と環境にやさしい賃金制度等」
持続可能経営の視点から人事・労務システムをいかに改革するかを
社会保険労務士の立場からお話を伺うことが出来ました。
第3部では、横浜市内の環境に関する助成金情報等を説明していただきました。
受講者の方々は、真剣な眼差しで受講に臨み、質疑応答に入ると
「横浜市内の環境経営に関する助成金について、次回、さらに詳しく伺いたい」
との声も上がり、
受講者達の持続可能経営の実現に対する意識の高さが見られるセミナーでした!

こんにちは。米田です。
先日、大学時代の旧友と一年ぶりに集まって
お酒を飲み交わす機会がありました。
母校である某大学のある池袋の居酒屋にて
かつてのサークルの仲間たちとの同窓会というわけです。

その日私は、あえて待ち合わせの時間より
はやい時間に池袋に着き、懐かしさに任せてかつて遊びほうけた街を
散策していたのですが、
そこには当時の面影こそ残しているものの、
毎日飲み明かした居酒屋や授業をサボってたむろしていた喫茶店など
多くの「思い出の場所」が跡形もなく消えていて、
真新しいお店や娯楽施設が当たり前のように鎮座していたのです。

大学時代を謳歌した街並みの変化は「絶対にもう戻れない時」を
強調されているようでどこか寂しく悲しいものでした。
しかし、そういった感情はある意味では
間違っていたのだとその後の飲み会で強く感じさせられたのです。
それぞれ社会にでて以来初めて再開した旧友との会話は
相変わらず楽しいものでおおいに盛り上がったのですが、
会話の内容は次第にそれぞれ仕事の話や将来のビジョンというような、
かつての自分たちでは考えられないものになっていきました。
そこには久しぶりに見た池袋の街同様、どこか寂しさを感じさせるものが確かにありました。
しかし、ひとつ気がついた事がありました。
かつてとは違った顔で話す旧友のその顔は間違いなく輝いていたのです。
「ああ、この寂しさは成長というやつなのだな。」
彼らの笑顔は至極単純明快なひとつの答えを教えてくれました。
過去を振り返ったとき、
それがすばらしいものであるほどもう戻れない悲しさを感じてしまうものです。
しかし、彼ら旧友との会話を通して私は感じました。
「この人たちに置いていかれたくない、
いやこの中で誰よりも輝いて今を語れるようになりたい」と。
そのためには自分も精一杯今をがんばって大きな夢に向かって挑戦し続けなくては、
いやそういうふうに生きていたいものだ。
戻れない日々や楽しかった馴れ合いを懐かしむよりも
大切な事をかつての悪友達に教えてもらった貴重な同窓会でした。
あ、その後お酒が進むにつれて大学はおろか
みんな幼稚園時代まで頭の中が後退していったのはご愛嬌。
いやはやアルコールは怖いですね・・・

今、「システムシンキング」という思考法が注目されています。
複雑化する現代において、何か一つの事象や仕組みにばかり気をとられると、
偏った認識で全体を把握できないまま物事が進み、
間違った解決法で誤った結果に至ってしまったり、
いつまでも成果にたどり着かないまま組織が疲弊していく、
などということもしばしばです。
そのような「木を見て森を見ず」という状態ではなく俯瞰的な視点で
物事を捉えるリーダーに必要な思考法の一つが
この「システムシンキング」です。
最近は、自社の昇進昇格試験に用いる企業も増えてきました。
例えば、「残業時間が多い」という組織の課題に対して、
「アルバイトを一人採用する」という解決法を選んだとしましょう。
ところが、アルバイトが仕事に加わっても、一向に従来のメンバーの
残業は減らない。
そこで、改めて現状把握してみると、
「業務分担があいまいで無駄な作業が多い」
「チームワークが悪く連携ができていない」
「チームの目標が見えず、方向性がバラバラ」
といった現状が見えてきて、
各々の状態を解決するための手段をとった結果、
そのチームの残業時間が減り、一人採用したことでより組織のパフォーマンスが
上がった、という結論に至る場合もあります。
私たちの目に見えるのは、組織の問題の氷山の一角でしかありません。
また、私たちは「”見たこと”を感じ、考える」のではなく、
「”感じたこと”を見て、考える」というように
主観で捉えていることもあります。
複雑系の世の中を正しく進み、成長し続ける組織を創るために、
この「システムシンキング」という思考法は、
リーダーこそ身に付けるべきものです。
★㈲人事・労務では、この「システムシンキング」に関する講義も
取り入れた「課題抽出演習」をリーダー向けに実施しています。
詳しくは、
http://www.jinji-roumu.com/inbp_new2.html

こんにちは。西園寺です。
先日、天気が良く、のんびりお買い物がしたかったので、
お台場のアウトレットへ行ってきました!
お台場へ買い物に行った際、
テラス部分で、大道芸人さんが出し物をしていて、とても面白かったので、ご紹介します。
偶然通りがかったテラスで大道芸をやっており、
ちょうど始まったところらしく、
人がまばらで、すぐ終わるのかな、と軽い気持ちで見てみることにしました。
少し距離を置いてみていたところ、
「後ろ通行人が通るから、もっと前に来なよ~」
「何かすごいことやっている風にしたいので、拍手をたくさんください!」
といったことを大道芸人さんはおっしゃっていて、
技ももちろんすごかったのですが、言葉でも楽しませていただきました。
すぐ終わると思っていたのですが、
どんどん人が集まってきて、
また、トランクから道具が次々と出てきて、グングン引き込まれていきました。

最後は大掛かりに、見物客の中から力持ちそうな男性6人に声を掛け、
お客さん6人と綱を使った芸を披露してくださいました。
大道芸人さんが帽子を差し出し、
「私がいただいているのはこの場所の許可のみで、
ギャラなどは一切いただいておりません。・・・誰か・・・。」
と四角いお札を求めるジェスチャーをしている時は、
少し切なくなりました。
お金の面ではたいそうな苦労をしている様子でしたが、
でも紛れも無くこの人はプロで、炎天下で汗だくになって、みなさんの笑顔と拍手が何よりです、
と言っている姿にも、感動しました。

|